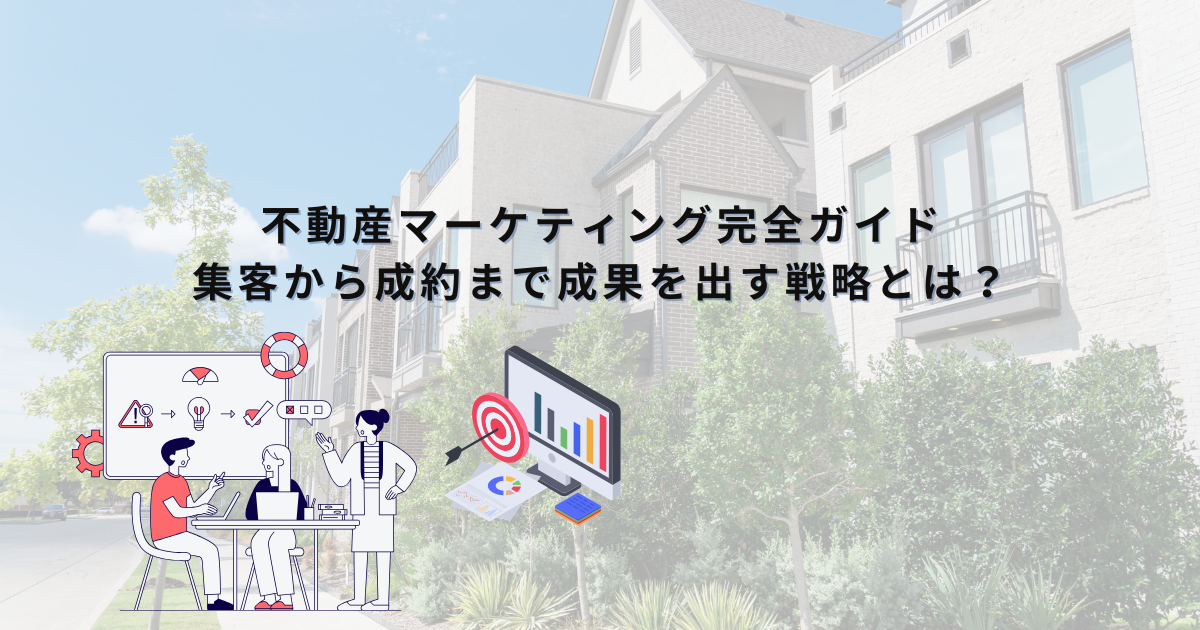近年、不動産業界を取り巻く環境は急速に変化しています。インターネットの普及により、物件探しの起点が店舗からWebやSNSへとシフトし、顧客の意思決定プロセスもより複雑かつ慎重なものになりました。こうした中で、「ただ広告を出すだけ」では思うような反響や成約を得ることが難しくなっており、不動産会社にはより戦略的なマーケティング活動が求められています。
本記事では、不動産業界におけるマーケティングの重要性を改めて確認したうえで、Web広告やSNS、SEO、CRMなどを活用した効果的な手法を体系的に解説します。さらに、顧客の購買行動に沿ったコンテンツ設計やKPIの数値管理、よくある失敗とその改善策など、実務に役立つノウハウを盛り込みました。不動産集客や売上アップに悩む企業・担当者にとって、確かな手がかりとなる内容をお届けします。
不動産業界におけるマーケティングの重要性とは

ここでは、なぜ今「不動産業界」においてマーケティングが必要不可欠なのか、その背景と理由を詳しく解説します。業界特有の営業体制、顧客行動の変化、デジタル化への対応など、根本的な構造変化が求められている現状を理解することが、効果的な集客施策の設計に役立ちます。
顧客の情報収集行動の変化に対応する必要性
現代のユーザーは、物件探しを始める前からGoogle検索やポータルサイト、YouTube、SNSなどを使って情報収集を行っています。以前のように「通りがかりで店舗に入る」「チラシを見て電話する」といった行動パターンは少なくなり、店舗に来店する時点ではすでに比較検討が終わっているケースも多くあります。このようなユーザー行動の変化に対応しなければ、機会損失につながるのです。
そのため、自社サイトの強化、SEOやMEO対策、広告運用、LINE公式アカウントやInstagramなどのSNSによるタッチポイント創出が重要になります。つまり、「探される会社」から「見つけてもらえる会社」になるための戦略が求められているのです。
店舗集客からWebマーケティングへの転換
従来の不動産業界は、立地の良い店舗を構えて来店を待つ「待ちの営業スタイル」が主流でした。しかし、今やWeb上でいかにユーザーとの接点を持ち、問い合わせや内見予約につなげられるかが、集客力の差を決定づける要素となっています。
特に都市部では競合が多く、単純な「広告出稿」だけでは費用対効果が合わないこともあります。そのため、適切なキーワード設計と広告配信、LPO(ランディングページ最適化)、CVR改善のためのフォーム設計など、マーケティング要素を全方位で組み合わせた施策が不可欠になります。
不動産ビジネスの長期的成長に欠かせない投資
不動産取引は単価が高く、1件あたりの売上が大きい反面、獲得までのリードタイムが長く、顧客が離脱しやすいという特性があります。だからこそ、継続的な情報提供や顧客との関係構築が重要であり、それを実現するのがマーケティング活動です。
また、企業としてのブランドイメージや信頼感の醸成も、コンテンツ発信やSNS、口コミ戦略を通じて築いていく必要があります。短期的な成果だけを追うのではなく、長期的な視点で「不動産ビジネスを育てていく」ための投資として、マーケティングは今後ますます不可欠な要素となるでしょう。
不動産マーケティングで活用される主な手法

ここでは、不動産業界で実際に活用されている代表的なマーケティング手法について詳しく解説します。Web広告やSNS、SEO、自社メディアなど、デジタルチャネルを中心に、各手法の特徴や導入時のポイントを整理し、自社に合った施策を選定するための判断材料を提供します。
Web広告(Google広告・Yahoo!広告)の活用
不動産集客において、Google広告やYahoo!広告といったリスティング広告は非常に有効です。ユーザーが「エリア名+賃貸」「駅名+新築マンション」といった検索を行った瞬間に広告を表示できるため、成約に近い層にダイレクトにアプローチできるのが大きな利点です。
さらに、検索連動型広告に加えて、ディスプレイ広告を活用することでリマーケティング施策も可能になります。サイトに訪問したものの問い合わせに至らなかったユーザーを追跡し、後日再び広告を表示して再接触することで、コンバージョン率を向上させることができます。
費用面ではクリック課金制のため、予算管理がしやすい一方で、キーワードの選定やエリア設定を誤ると無駄クリックが発生しやすく、広告費の浪費につながるリスクもあるため、運用の精度が求められます。
参考:GoogleとYahoo!のリスティング広告に関して徹底解説!違いについても徹底比較
広告出稿とは?料金や流れ、出稿先について解説!
SNS広告(Instagram・Facebook)の活用
InstagramやFacebookなどのSNS広告は、物件情報のビジュアル訴求やブランド認知の向上に役立ちます。特にInstagramは、内装写真やルームツアー動画などとの相性が良く、視覚的なインパクトで興味を引くことができます。
エリアや年齢、興味関心などのターゲティング精度が高く、特定の層にピンポイントで訴求することも可能です。また、LINE広告と連携することで、見込み客への継続的なフォローにもつながります。
SNS広告は即効性よりも、潜在層への認知拡大や、リスト獲得を目的とした長期戦略としての活用が向いています。ブランドイメージを高めつつ、見込み客との接点を多く持つことで、中長期的な売上につなげていく施策です。
自社サイトとSEOによる集客
自社サイトは、会社の信頼性や物件の魅力を伝える基盤であり、最も重要な資産の一つです。SEO(検索エンジン最適化)によって「地域名+賃貸」「駅名+不動産会社」といったキーワードで自然検索からの流入を増やすことで、広告費をかけずに集客が可能となります。
また、物件情報の更新性や、地域情報・お役立ちコラムの発信などもSEO評価に大きく影響します。たとえば「◯◯駅の住みやすさ」「ファミリーにおすすめの◯◯エリア賃貸」など、ローカルキーワードを活用することで、競合が少ないロングテール流入も狙うことができます。
SEOは成果が出るまで時間がかかるものの、安定的に集客できるため、広告施策との併用が理想です。短期施策と長期施策のバランスを取ることが、効果的なマーケティング運用には欠かせません。
顧客の購買プロセスを踏まえた戦略設計

ここでは、不動産を探すユーザーがどのようなプロセスで意思決定に至るのか、マーケティングにおいて重要となる「購買プロセス」の全体像を整理し、それぞれの段階で最適な情報提供やアプローチ方法について詳しく解説します。特に、高額かつ慎重な検討を要する不動産領域では、段階ごとの理解が集客成果に直結します。
認知→興味→検討→行動のフロー理解
不動産の購入・賃貸に至るまでの購買行動は、一般的に「認知 → 興味 → 検討 → 行動」という段階を踏んで進んでいきます。これはマーケティングにおけるファネル型モデルの基本であり、それぞれの段階でユーザーが求める情報や心理状態は異なります。
「認知」フェーズでは、ユーザーはまだ物件を探し始めたばかりで、住みたいエリアや希望条件も漠然としています。この段階では広告やSNS投稿、ポータルサイトへの掲載などを通じて、まずサービスや物件を「知ってもらう」ことが目的です。
「興味」フェーズでは、すでに関心がある分野に目を向けており、エリアや物件タイプの条件が徐々に明確になってきます。資料請求やLINE登録、セミナー参加など、ユーザーの行動がアクティブになっていきます。
「検討」フェーズでは、他社比較や価格、立地条件などの詳細に踏み込んだ情報収集が行われ、「行動」フェーズでようやく内見や問い合わせ、申し込みへとつながります。各段階を飛ばさず、スムーズに次のステップへ移行させる戦略が求められます。
各フェーズで適したコンテンツの出し分け
ユーザーの購買ステージごとに提供すべきコンテンツは明確に異なります。たとえば、「認知」段階では、不動産会社のブランドやエリアの魅力を伝えるようなライトなコンテンツが有効です。写真や動画を活用したSNS投稿やYouTubeチャンネルでのルームツアー、ブログでの暮らし紹介などが、この段階に適しています。
「興味」段階では、少し踏み込んだ内容が必要です。物件情報の詳細、ローンの考え方、エリア比較、生活利便性など、より実用的な情報を盛り込んだ記事や動画を提供することで、信頼感を醸成します。
「検討」フェーズでは、他社比較や価格交渉の視点も入ってくるため、問い合わせのハードルを下げる特典付きキャンペーン、オンライン個別相談、見学会などの導線強化が重要です。そして「行動」フェーズでは、LP(ランディングページ)の最適化やフォーム改善、即時対応体制を整えることで、最後の一押しを成功に導きます。
このように、段階ごとにユーザーが求めている情報を正確に把握し、適切なタイミングで提供することが、無駄な広告費の削減にもつながり、成約率の最大化を実現します。
CRMを活用したフォロー体制の構築
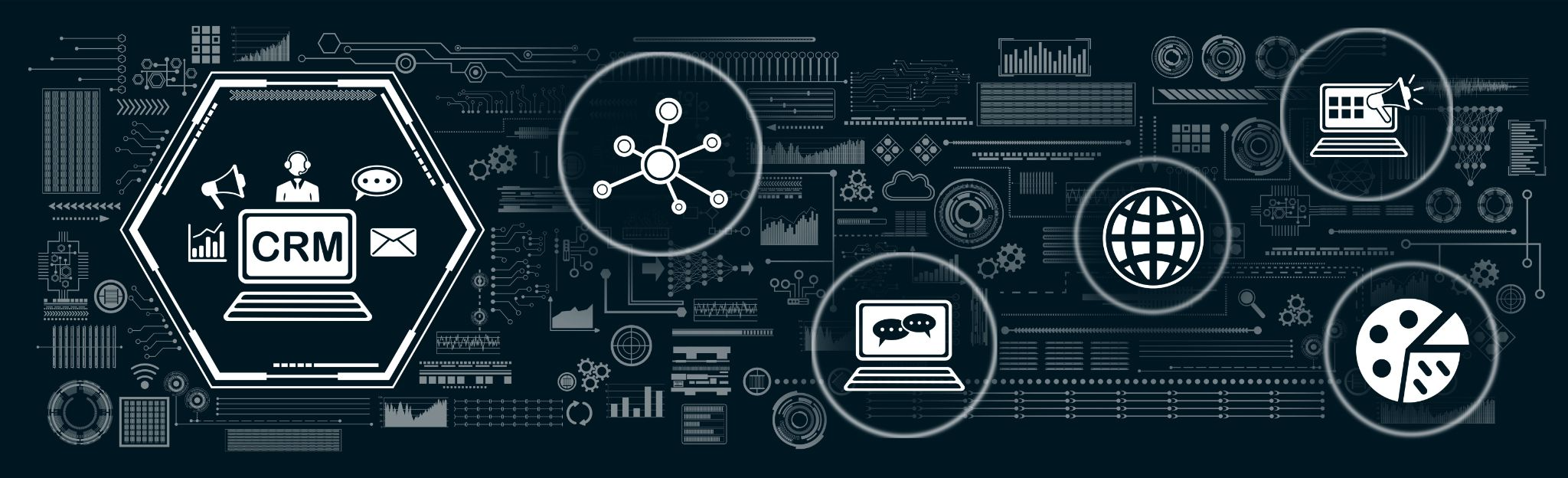
顧客の行動データを記録・活用するには、CRM(顧客管理システム)の導入が非常に有効です。特に不動産のように検討期間が長く、複数の接点が存在する業界では、過去の接触履歴や反応傾向を可視化することで、最適なフォローのタイミングと手段を選ぶことができます。
たとえば、Webフォームから資料請求を行ったユーザーに対しては、1週間後にエリア別の新着物件情報をメールで送る、興味を示した物件がある顧客に対しては、LINEでリマインドを行うといった活用が可能です。
さらに、CRMを使えば、反応履歴に基づいたステップメール配信や、営業担当の対応ログ記録、成約見込みのスコアリングも実現でき、属人的な営業活動から脱却する手助けにもなります。マーケティングオートメーションと連携することで、より精度の高い顧客育成を図ることも可能です。
顧客が何に反応し、どのような行動を取ったかを蓄積・活用する体制を整えることは、将来的な経営戦略や広告投資判断にも直結する重要な取り組みと言えるでしょう。
不動産マーケティングで使えるチャネルと媒体

ここでは、不動産集客において活用される主な広告チャネルや媒体の種類と、それぞれの特徴、活用法について解説します。チャネルごとの特性を理解し、目的に応じて組み合わせて活用することで、反響の最大化と費用対効果の向上が期待できます。
オンラインチャネル(検索広告、SNS、YouTubeなど)
不動産業界において、オンラインチャネルは今や集客の中心的な存在となっています。なかでも代表的なものが「検索連動型広告(リスティング広告)」です。GoogleやYahoo!などで「○○駅 新築マンション」「○○市 賃貸」などのキーワード検索を行ったユーザーに対し、即座に広告を表示できるため、成約に近いユーザーへ効率的にアプローチできます。
SNS広告も有効です。FacebookやInstagram、LINE、TikTokなどは、ターゲットの属性(年齢、居住地、家族構成など)に基づいた配信が可能で、ブランディングや認知拡大に強みを持ちます。特にビジュアルで訴求できる住宅・インテリア系コンテンツとの相性は良く、ルームツアー動画や施工例を交えた投稿が反応を集めやすくなります。
さらに、YouTube動画広告も注目されています。モデルルーム紹介やエリア紹介、購入体験談などをストーリー仕立てで見せることで、ユーザーの興味・関心を自然に引き出すことが可能です。特に検討段階が深まっているユーザーに対しては、動画が購入意欲を後押しするコンテンツになります。
オフラインチャネル(新聞折込、ポスティング、イベントなど)
デジタル化が進む一方で、地域密着型の不動産業においてはオフラインチャネルも依然として重要です。特に、エリア内の認知拡大を狙う場合や、高齢層をターゲットにする場合には効果的です。
新聞折込広告は、ローカルの読者層に確実にリーチできる手段であり、特定の販売圏に物件情報を届けるのに適しています。また、費用はかかりますが、毎週決まったタイミングで出稿することで安定した露出が可能です。
ポスティングは、ターゲットとなる地域や物件周辺にダイレクトにチラシを届けられる手法です。特に「徒歩圏の住み替えニーズ」などを掘り起こすのに向いており、マンションの掲示板やポストへの投函など地道な活動が功を奏することもあります。
また、地域でのイベント出展や住宅見学会なども信頼構築に効果的です。直接顔を合わせられる接点は、オンラインでは得られない信頼感を醸成でき、他社との差別化にもつながります。
ポータルサイト・自社サイトの活用
不動産業界では「SUUMO」「HOME’S」「アットホーム」などの不動産ポータルサイトが重要な集客媒体となっています。これらは圧倒的な集客力を誇る反面、掲載費用がかかるため、費用対効果を見ながら適切に活用することが大切です。
ポータルサイトの活用では、ただ物件を掲載するだけでなく、魅力的な写真、間取り、コメントなどのコンテンツ強化が成約率を大きく左右します。また、掲載順位を上げるためにオプション費用をかける必要もあるため、競合とのバランスも見極めが重要です。
一方で、長期的には自社サイトへの集客も強化すべきです。自社サイトには「ブランド訴求」「差別化情報」「資料請求フォーム」「LINE連携」「セミナー情報」など、自由度の高いコンテンツを設計できます。SEOやGoogle広告などで自社サイトに直接流入させ、反響を獲得する動きも一般化しています。
ポータルサイトに依存せず、自社資産としてのWebサイトをしっかり育てていくことが、将来的な経営の安定とコスト最適化に大きく貢献します。
不動産マーケティングにおけるよくある失敗と課題
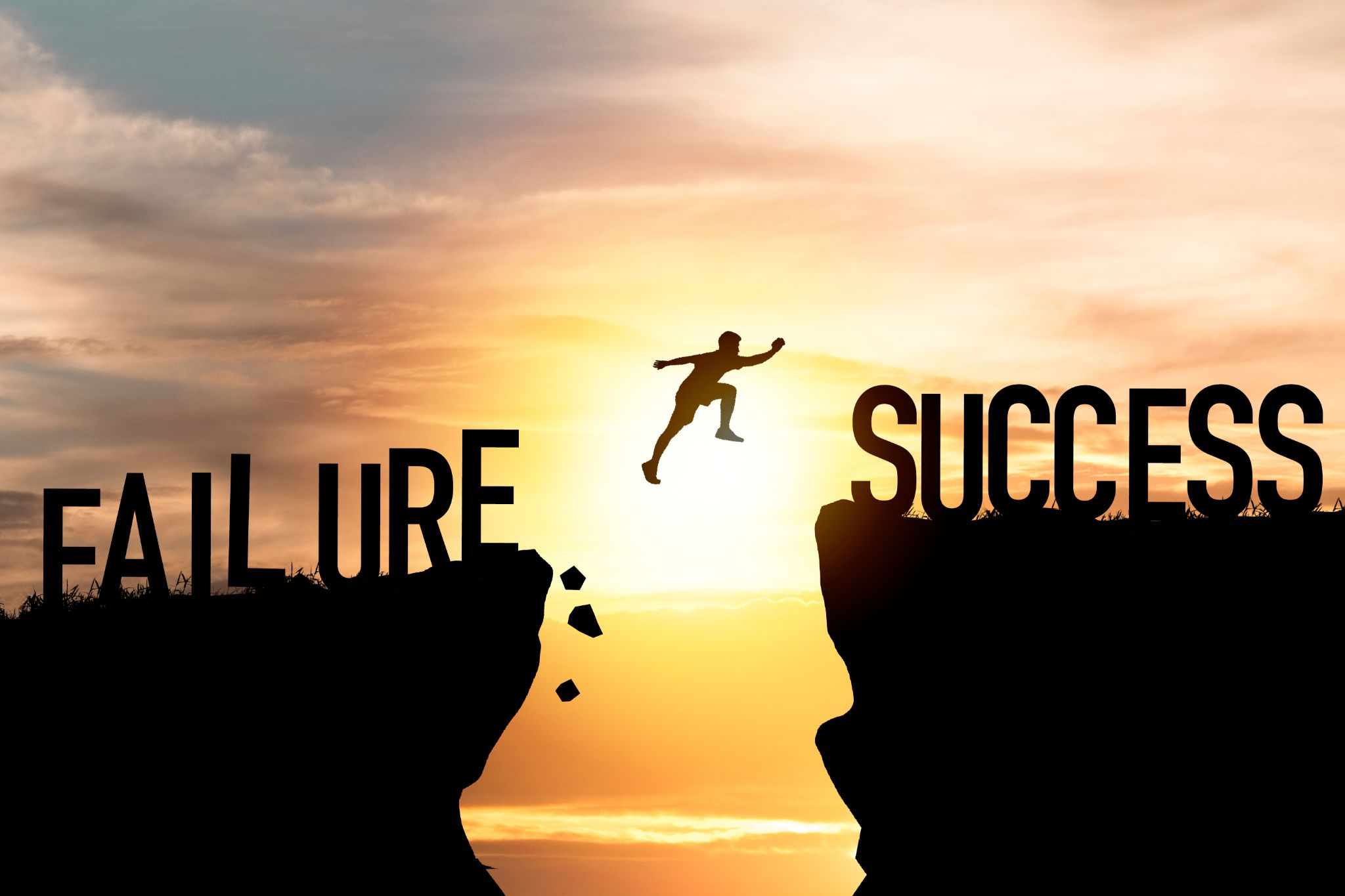
ここでは、不動産業界におけるマーケティング施策が思うような成果を生まない原因と、よくある失敗事例について解説します。広告を出しても問い合わせが増えない、もしくは問い合わせがあっても契約に至らないといった悩みは多くの企業で共通しています。成功事例と同様に、失敗パターンを理解することで、今後の改善策を見出す手がかりとなります。
反響はあるが成約に結びつかないケース
広告やWeb施策によって反響は得られているものの、実際の内見や成約につながらないという課題は、不動産業界でよくある悩みのひとつです。見込み客が物件情報に興味を持って問い合わせをしたにもかかわらず、具体的な行動に移らない場合、導線や接点のどこかにボトルネックが存在していると考えられます。
例えば、広告で「即入居可」「駅徒歩5分」などの強い訴求をした場合でも、現地を訪れてみると物件の状態が想像と異なっていたり、写真と間取りが実態と食い違っていたりすると、ユーザーの信頼を損なってしまいます。また、問い合わせ後のレスポンスが遅い、担当営業の対応が淡泊で説明不足など、接客フェーズにおける体験の質も大きく影響します。
反響から成約までを一つのプロセスとして捉え、広告文・LP(ランディングページ)の内容と現地対応・商談内容の一貫性を保つことが非常に重要です。また、商談化しない問い合わせがどの段階で離脱しているのかを把握する仕組みを整えることも、改善の第一歩となります。
顧客データの蓄積・活用ができていない
せっかく反響を得ても、そのデータが適切に蓄積・管理されていないケースも少なくありません。特に中小規模の不動産会社では、顧客情報を個々の担当者が属人的に管理していることが多く、会社全体としてマーケティング活動に活用できていないという問題があります。
例えば、一度問い合わせをくれた顧客がどの物件に興味を持ち、どの段階でやり取りが止まったのかといった履歴情報が記録されていなければ、再アプローチのタイミングや内容が的外れになってしまう可能性があります。逆に、CRM(顧客管理システム)を導入し、顧客の行動履歴や属性、反応履歴を蓄積することで、メールマーケティングやLINE配信、リターゲティング広告などを通じた有効なフォローアップが可能になります。
また、接客中に得た情報や、問い合わせ後の行動(サイト再訪、資料請求、比較検討など)もマーケティング資産として蓄積することで、中長期的な成約率の向上につながります。顧客データは単なる「連絡先」ではなく、マーケティング施策の精度を高めるための基盤であると認識すべきです。
メディアごとの目的が不明確なまま運用している
複数の広告媒体を並行して活用している企業も増えていますが、各メディアの役割を明確に定めないまま運用してしまうと、費用対効果が低くなったり、無駄な配信につながったりします。
たとえば、Google検索広告はニーズ顕在層へのアプローチに適しており、成約率も比較的高い傾向にあります。一方、YouTube広告やディスプレイ広告は潜在層への認知拡大を目的とするため、直接の問い合わせにつながらないこともあります。しかし、これらの特性を理解せず、すべての広告で「即時の反響」を求めると、成果に対する期待と実態のギャップにより「効果がない」と判断されてしまう恐れがあります。
また、SNSやメールマガジン、ポスティングなどのオフライン施策についても同様です。「どのチャネルで何を目的とし、どのようなKPIを設定するか」をあらかじめ決めておかないと、予算配分の最適化や改善施策の優先順位があいまいになってしまいます。
広告運用においては、「媒体選定→目的明確化→KPI設定→定点観測→改善」のサイクルを設けることが、戦略的なメディア運用には不可欠です。
成果を上げるための改善アプローチとKPI設計

不動産マーケティングにおいて成果を継続的に上げるには、感覚や過去の経験則に頼るのではなく、定量的なデータに基づいた改善サイクルを構築することが不可欠です。この章では、具体的な指標(KPI)を使った評価方法と、それをどのように分析・改善に活かすべきかを解説します。また、広告運用・Webサイト改善・営業対応を部門横断で連携させるための考え方についても紹介します。
CPA・CVR・LTVなど数値で施策を評価する
マーケティング施策の成果を評価するためには、「なんとなく成果が出ている」ではなく、明確な指標(KPI)を設定することが重要です。不動産業界で特に注目すべきKPIとして、以下のような指標が挙げられます。
- CPA(顧客獲得単価):1件の問い合わせや成約を獲得するためにかかった広告費を示す指標。広告費を最適化するための基準となります。
- CVR(コンバージョン率):広告クリックやLP訪問から、問い合わせなどの成果に至った割合を表します。LPやバナーなどのクリエイティブ改善に活用できます。
- LTV(顧客生涯価値):1人の顧客が将来的に企業にもたらす利益の合計。賃貸管理や再販など中長期的な関係が重要な不動産業では特に重視すべき指標です。
これらの指標を定期的にモニタリングし、改善施策のPDCAサイクルを回すことで、広告費の無駄を減らし、成約効率を高めることが可能になります。KPIを設定する際には、短期(CVRやCPA)と中長期(LTVやリピート率)の両面からバランスよく設計する視点が求められます。
GA4やCRMでの分析と改善のサイクル化
施策を評価するうえで、Google Analytics 4(GA4)やCRMといった分析ツールの活用は欠かせません。GA4では、WebサイトやLPの訪問データ、ユーザーの流入元やコンバージョンパスを可視化することができ、どのチャネルが成果に結びついているかを明確に把握できます。
たとえば、広告経由でLPに流入したユーザーがどのくらいスクロールし、どのページで離脱しているかを確認することで、LPの構成やコンテンツに対する改善点が見えてきます。また、GA4とGoogle広告を連携することで、広告ごとのコンバージョン効率やクリック単価などの指標を一元的に管理することも可能です。
一方、CRMでは、問い合わせ後の商談状況や成約までのプロセスを管理・分析することができます。GA4でWeb上の行動を、CRMで商談以降のフェーズを追うことで、より網羅的な顧客ジャーニーの分析が実現します。
これらの分析基盤を整えたうえで、週次・月次などの定点観測を行い、「どの施策がどのような影響を与えたのか」「どの改善が功を奏したのか」を可視化する体制を整えることが、継続的な成果改善の鍵となります。
広告・サイト・営業部門の連携強化
不動産マーケティングの現場では、広告運用・Webサイト制作・営業現場が別のチームや外注先に分かれていることも多く、部門間での情報共有や連携が不足しがちです。しかし、本来これらは分断されたものではなく、ひとつの顧客体験をつくる要素として連動させる必要があります。
たとえば、広告施策で集めた見込み客が問い合わせをしても、営業担当がその顧客の流入経路や興味を知らなければ、ヒアリングの切り口や提案内容がズレてしまい、せっかくの機会を失うことになりかねません。これを防ぐためには、広告のキーワードやキャンペーン名、LPの内容といった情報を営業部門と共有する仕組みが求められます。
また、営業現場から得られる「実際に成約につながった要因」や「顧客が迷っていたポイント」などの定性情報を広告やWeb制作側にフィードバックすることで、より実態に沿ったメッセージ設計や訴求ポイントの最適化が可能になります。
成果を最大化するためには、部署間の縦割り構造を超えた「マーケティングと営業の連携体制」を築くことが欠かせません。そのためには、定例ミーティングやCRMでの共有コメント機能などを通じて、日常的に情報の流通が行われる仕組みづくりが重要となります。
株式会社ArchRise は不動産マーケティングに対応しています
株式会社ArchRiseは、不動産マーケティングに関して豊富な実績を有しています。また、SEO対策やSNS広告、コンテンツマーケティングなど多岐にわたるWebマーケティングサービスを提供しています。豊富な実績とデータに基づいた最適な運用で、クライアント、企業の目標達成を弊社が全力で支援します。
ご相談は無料ですので、興味があればぜひお気軽にお問い合わせください。
まとめ
不動産マーケティングで成果を上げるためには、単なる広告配信や集客施策にとどまらず、顧客の購買プロセスを深く理解し、段階に応じた情報提供と接点づくりを行うことが重要です。CPAやCVR、LTVといった指標をもとにKPIを設定し、データに基づく改善を継続的に行うことで、より高い成約率と費用対効果を実現できます。また、WebサイトやSNS、広告、営業活動といった各チャネルを分断させず、CRMやGA4を活用して部門間の連携を強化することも成果に直結します。不動産業界特有の課題や失敗パターンを理解し、時代に合った柔軟なマーケティング戦略を設計・運用することが、今後ますます求められていくでしょう。