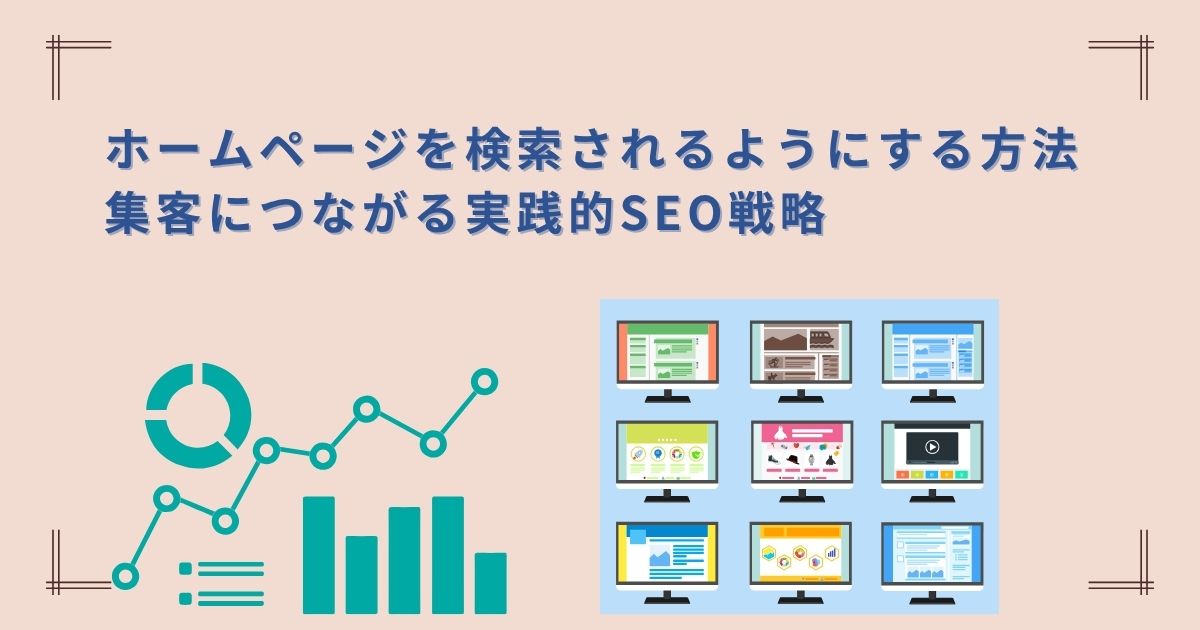ホームページを公開したのに、検索しても自社サイトが出てこない――そんな悩みを抱えていませんか?
せっかく時間をかけて作ったホームページも、検索に表示されなければ存在しないのと同じです。アクセスが伸びない、問い合わせが来ないといった課題の多くは、「検索されない」ことが原因にあります。
検索に引っかからない理由は、SEO対策が十分にできていない、Googleにインデックス登録されていない、またはサイト構造やコンテンツの問題など、さまざまです。
まずは原因を明確にし、正しい対策を行うことが大切です。
この記事では、
- ホームページが検索に引っかからない主な原因
- 検索されるようにするための仕組み
- 検索順位を上げるための具体的な対策
について、初心者でも分かるように解説します。
自社のホームページが検索結果に表示されるようになれば、アクセス数の増加や認知度向上、問い合わせ獲得にもつながります。
「ホームページを検索されるようにしたい」「上位表示を目指したい」とお考えの方は、ぜひ最後までご覧ください。
検索に引っかからないホームページの原因
検索に引っかからないホームページには、必ず何らかの原因があります。
ホームページを公開しても、すぐに検索結果へ表示されるとは限りません。
「ホームページを開設してしばらく経つのに検索結果に出てこない」
「社名で検索しても表示されない」
そんな場合は、Googleの検索エンジンに正しく登録(インデックス)されていない可能性が高いです。
検索に表示されない要因は、インデックス未登録だけでなく、SEO設定の不備、重複コンテンツ、更新不足など複数あります。
まずは原因を正しく把握し、一つずつ改善していくことが検索結果に表示させる第一歩です。
ここからは、ホームページが検索に引っかからない代表的な原因を具体的に紹介していきます。
検索でヒットするための設定(インデックス登録)がされていない
ホームページが検索でヒットしない場合、まず確認すべきなのがインデックス登録(Googleへの登録設定)です。
インデックス登録とは、Googleの検索エンジンに自社のホームページを認識してもらい、データベースに保存してもらうことを指します。
どれだけデザイン性の高いホームページを制作しても、インデックス登録がされていなければ、検索結果に表示されることはありません。いわば「世の中に存在していないホームページ」と同じ状態になってしまうのです。
検索エンジンがホームページを認識していないケース
検索エンジンがホームページを認識していないと、クローラー(Web上の情報を収集する自動プログラム)がページ情報を取得できず、データベースに登録されません。
この場合、検索結果に表示されないだけでなく、Googleからは「存在しないページ」として扱われます。
たとえば、サイト制作時に「noindexタグ(インデックスしない設定)」が誤って埋め込まれていたり、robots.txtファイルでクローラーのアクセスを制限していると、Googleがページを読み込めません。
まずは、自社のホームページがGoogleにインデックスされているかを確認しましょう。
Google検索で
site:自社ドメイン(例:site:example.com)と入力すると、インデックス状況を簡単に確認できます。
表示されなければ、インデックス登録がまだ行われていない可能性が高いと考えられます。
検索エンジンのガイドラインに違反している
検索に引っかからない原因の一つに、検索エンジンのガイドライン違反が挙げられます。
Googleの定めるガイドラインに違反している場合、検索順位の大幅な低下や、最悪の場合インデックス削除といったペナルティを受ける可能性があります。
その結果、ホームページが検索結果にまったく表示されず、実質的に「存在していないサイト」として扱われてしまうこともあるのです。
ガイドライン違反の主な例としては、次のようなケースがあります。
- 隠しテキストや不自然なリンクの設置
- オリジナルコンテンツがほとんど存在しない
- 他サイトの内容をコピー・使い回した重複コンテンツ
- 自動生成されたAIコンテンツ(意味の通らない文章など)
- 不正なリダイレクトやクローキング(検索エンジンとユーザーで内容を変える行為)
- 相互リンクやリンクプログラムの乱用
- 関係のないキーワードの過剰使用
これらはすべてGoogleの「検索エンジン最適化スターターガイド」や「ウェブマスター向けガイドライン」で禁止されている行為です。
ペナルティを受けているか確認したい場合は、Googleサーチコンソールでメッセージ通知や警告をチェックしてみましょう。
キーワード検索する人の欲しい情報がホームページ内にない
また、ホームページに訪れるユーザーの「検索意図」に沿った情報がない場合も、検索結果に表示されにくくなります。
検索キーワードを多く盛り込んでいても、ユーザーが求めている答えが掲載されていなければ意味がありません。
たとえば、「カフェ 勉強」と検索しているユーザーは勉強しやすいカフェを探しているのであって、単に“カフェの歴史”を知りたいわけではないのです。
Googleは「キーワードが含まれているか」よりも、「検索した人の疑問や悩みを解決できるページか」を重視します。
そのため、まずはユーザーがどんな情報を求めて検索しているのかを分析し、検索意図(サーチインテント)に合ったコンテンツ作りを意識することが大切です。
コンテンツの質が低い
コンテンツの質が低いホームページは、検索に引っかかりにくくなります。
Googleはユーザーにとって価値のある情報を上位に表示するため、オリジナリティがなく内容の薄いページや他サイトのコピー・機械的に生成された文章などを低く評価します。
質の低いコンテンツが多いと、検索エンジンのガイドライン違反と判断され、ペナルティを受ける可能性もあります。結果として、検索順位が大きく下がったり、インデックスから除外されたりするリスクもあるのです。
高品質なコンテンツとは、ユーザーの疑問を的確に解決し、具体的で信頼性の高い情報を提供しているページのことです。単に文字数を増やすのではなく、「ユーザーが求める答えにどれだけ寄り添えているか」を意識して制作しましょう。
また、古くなった情報を放置しておくことも品質低下の要因になります。定期的なリライトや最新情報の追加を行い、常にユーザーにとって価値のあるページを維持することが大切です。
ホームページが検索に引っかかるようにする仕組み
ホームページを開設しただけでは、検索結果に表示されることはありません。
Googleで検索にヒットさせるためには、検索エンジンがどのようにホームページを認識・評価しているかを理解することが大切です。
検索エンジンでは、以下の3つのプロセスを経てホームページが検索結果に表示されます。
① クロール(ホームページを探す)
「クロール」とは、検索エンジンのロボット(クローラー)がインターネット上を巡回し、ホームページの情報を収集することを指します。
クローラーはHTMLやPHPなどのファイル構造を読み取り、リンクをたどりながら新しいページを発見・解析します。
このクロールが正常に行われなければ、そもそも検索エンジンにページが見つけてもらえず、検索結果にも表示されません。
クローラーが巡回しやすいよう、内部リンクを整理し、サイト構造を明確にすることが重要です。
また、クローラーは一度だけでなく、定期的に巡回を繰り返します。
より早く認識させたい場合は、「Google Search Console(サーチコンソール)」からクロールのリクエストを送ることで、インデックス登録を促すことも可能です。
なお、新しく取得したドメインの場合、クローラーが訪問するまで数週間〜数か月かかることもあります。
② インデックス(ホームページを登録する)
クローラーによって収集されたページ情報は、Googleのデータベースに「インデックス(登録)」されます。
これは本でいう「索引」にあたる工程で、検索エンジンが「このページにはどんな内容が書かれているか」を整理・分類する段階です。
インデックスされていなければ、いくら優れたコンテンツを公開していても検索結果には表示されません。
「site:自社ドメイン」で検索し、自社サイトがインデックスされているか確認しておきましょう。
③ ランキング(検索順位を決める)
インデックス登録が完了すると、最後にランキング(順位付け)が行われます。
Googleは、ページの内容や被リンクの質、ユーザー満足度などを総合的に評価し、検索キーワードごとに順位を決定します。
このランキングを決める仕組みは「PageRank(ページランク)」と呼ばれ、数値が高いほど信頼性や価値の高いページとして評価されます。
Googleは特に「ユーザーファースト」を重視しており、理念である「Googleが掲げる10の事実」にも「ユーザーの利便性を最優先にする」ことが明言されています。
つまり、ユーザーにとって価値のある情報をわかりやすく提供するページこそが、検索上位に表示されるのです。
できるだけ早く検索結果に表示させるコツ
ホームページを公開しても、すぐに検索結果に反映されるとは限りません。
しかし、正しい手順を踏めばより早くGoogleの検索結果に表示させることが可能です。
ここでは、スピーディーに検索表示を実現するための具体的な方法を紹介します。
Google Search Consoleへ登録する
まずは Google Search Console(グーグルサーチコンソール) に登録しましょう。
これはGoogleが無料で提供している、ホームページのパフォーマンス管理・改善ツールです。
登録しておくことで、以下のようなデータが確認できます。
- どんなキーワードでユーザーが自社サイトを訪問しているか
- 各キーワードでの平均掲載順位
- ページがGoogleに正しくインデックスされているか
- 被リンクの数やクリック率(CTR)
登録自体は無料で、数分で完了します。
SEO対策を強化したい、あるいはホームページからの集客を伸ばしたい企業は、必ず導入しておきましょう。
Googleにインデックス登録を行う
次に、Googleにインデックス登録を依頼しましょう。
インデックス登録とは、Googleがあなたのホームページを「検索対象」としてデータベースに登録することです。
登録状況を確認するには、Googleの検索窓に以下を入力します。
- 「site:自社ドメイン」 → 登録済みのページが一覧表示される
- 「ホームページのタイトル」 → 検索結果に自社サイトが出てくるか確認できる
もし検索しても出てこない場合は、まだインデックスされていない可能性があります。
Google Search Consoleの「URL検査」機能を使い、ページURLを入力して「インデックス登録をリクエスト」してみましょう。
Googleにサイトマップを送信する
サイトマップの送信も効果的です。
サイトマップとは、ホームページ全体の構造を一覧化したファイルのことで、Googleに「このサイトにはこんなページがあります」と知らせる役割を持ちます。
サイトマップには以下の2種類があります。
- XMLサイトマップ:検索エンジンのクローラー用(SEO効果あり)
- HTMLサイトマップ:ユーザーがサイト構造を把握するためのページ
検索結果に早く表示させたい場合は、XMLサイトマップを作成してGoogle Search Consoleの「サイトマップ」メニューから送信しましょう。
SNSでホームページを拡散する
ホームページの存在をより多くの人に知ってもらうためには、自社のSNSでリンクを投稿するのも有効です。
SNS経由のアクセス増加は、クローラーがあなたのサイトを発見するきっかけにもなります。
Twitter(X)・Instagram・Facebook・LinkedInなど、ターゲット層に合ったSNSを活用し、投稿の中で自然にリンクを紹介しましょう。
また、SNSの投稿にリアクションが集まることで、ドメイン全体の信頼性(オーソリティ)も高まりやすくなります。
信頼できるWebサイトからのリンクを獲得する
信頼性の高いWebサイトからの被リンクを得ることは、SEOの中でも最も重要な要素の一つです。
Googleは、他のサイトからリンクを受けているページを「信頼されているページ」として評価します。
ただし、関連性の低いサイトやスパムリンクが多いと逆効果になるため注意が必要です。
業界内で信頼のあるメディア・取引先・自治体・パートナー企業などからのリンクを増やすよう意識しましょう。
質の高い被リンクをコツコツと積み上げることで、検索順位が上昇しやすくなります。
ホームページを検索順位で上位表示させる方法
ホームページを検索順位で上位に表示させることができれば、ユーザーの目に触れる機会が増え、クリック率(CTR)が向上します。
結果としてアクセス数が増加し、お問い合わせや資料請求、商品購入といったコンバージョンの向上にもつながります。
ただし、上位表示を実現するためには、やみくもに記事を増やすだけでは効果は出ません。
Googleが重視している「ユーザーファースト」の考え方を理解し、正しいSEO対策を段階的に行うことが大切です。
ここでは、ホームページを検索結果で上位に表示させるために押さえておきたい基本的な方法をわかりやすく解説します。
SEO対策で検索上位を目指す
ホームページを検索結果の上位に表示させるためには、まず SEO対策(Search Engine Optimization) を行う必要があります。
SEOとは「検索エンジン最適化」を意味し、Googleなどの検索エンジンで自社サイトをより上位に表示させるための施策を指します。
SEO対策を行う最大のメリットは、自然検索からのアクセス数(オーガニック流入)を増やせることです。
リスティング広告のように広告費を継続的に支払う必要がなく、長期的な集客効果が期待できます。
成果が現れるまでに時間はかかりますが、コストを抑えつつ見込み顧客へのアプローチを継続できる点がSEOの強みです。
検索キーワードの設定を最適化する
まず見直すべきは 検索キーワードの設定 です。
キーワード選定はSEO対策の基礎であり、上位表示できるかどうかを左右する重要な要素です。
検索数が多すぎるキーワードは競合が強く、上位表示を狙うのは難しくなります。
一方で、検索数が少なすぎるキーワードではアクセス増加が見込めません。
そこで、ユーザーの検索意図を考慮した サジェストキーワード(検索候補) を活用しましょう。
たとえば「ホームページ 集客」というキーワードなら、「ホームページ 集客 方法」「ホームページ 集客 仕組み」などの複合語を狙うことで、より具体的な検索意図に応えられます。
こうしたキーワード戦略は、ユーザーのニーズを満たす高品質なコンテンツ制作にも繋がります。
ユーザーニーズに沿った高品質なコンテンツ制作
検索順位を上げるためには、ユーザーの悩みや疑問を解決するコンテンツ を提供することが不可欠です。
単に自社の伝えたい情報を発信するだけでは不十分であり、検索ユーザーが求める答えを明確に提示する必要があります。
例えば、「ホームページが検索されない原因」を知りたい人には、仕組み・改善策・確認方法などを段階的に示すと効果的です。
また、自社製品やサービスを紹介する場合も、具体的な事例や実体験を交えた情報提供を意識すると良いでしょう。
自社での制作が難しい場合は、SEO専門の制作会社やマーケティングパートナーに相談 するのも一つの手段です。
タイトル・見出しの設定を最適化する
タイトルや見出しは、検索エンジンとユーザーの両方に対して重要なシグナルです。
キーワードを必ず含めることを意識し、なるべく左側(文頭付近)に配置 するのが効果的です。
また、見出し(H2・H3)にも関連キーワードを自然に含めましょう。
これにより、Googleがページ全体の内容を正しく理解し、関連する検索結果に表示されやすくなります。
一方で、キーワードを詰め込みすぎると「不自然な文章」と判断されるため、読みやすさとのバランスを意識することが重要です。
スマートフォン表示に対応させる
近年では、検索ユーザーの大半がスマートフォンからアクセスしています。
そのため、ホームページはスマートフォンでも見やすく操作しやすいデザインであることが求められます。
レスポンシブデザインを採用し、どのデバイスでもレイアウトが崩れないように設計しましょう。
また、PC版と同様に主要なコンテンツやボタンをスマートフォンでも快適に操作できるようにすることで、ユーザー満足度の向上にもつながります。
ページの読み込み速度を改善する
ページの表示速度は、SEO評価に直結します。
読み込みが3秒以上かかるページは、ユーザーの約半数が離脱すると言われています。
Googleが提供する「PageSpeed Insights」などの無料ツールを使えば、ページの表示速度を簡単に測定・改善できます。
画像の圧縮やキャッシュ設定、不要なスクリプトの削除などを行い、快適に閲覧できるサイトを目指しましょう。
ホームページの分析と改善を継続する
SEOは「一度やって終わり」ではなく、継続的な分析と改善 が不可欠です。
Google Analyticsなどのアクセス解析ツールを使い、アクセス数・滞在時間・離脱率・CV率などを定期的に確認しましょう。
データをもとに改善を重ねることで、ユーザーの行動傾向を把握でき、より最適な施策を導き出せます。
これにより、常に最新の情報と最適なユーザー体験を提供できるホームページに進化していきます。
競合他社の分析と調査を行う
最後に、競合他社のWebサイト分析 も忘れてはいけません。
競合サイトのコンテンツ構成やキーワード設定を確認することで、市場の傾向やユーザーニーズを把握できます。
特に、上位表示されているページはGoogleが「ユーザーにとって有益」と判断している証拠です。
自社との差分を分析することで、改善の方向性や独自性を見出せます。
また、定期的に競合サイトをチェックし、業界トレンドを反映したコンテンツづくりを意識することも大切です。
検索順位を上げるために最低限やっておきたい3つのこと
「検索に引っかかるようにしたい」という段階を超えて、「できれば検索順位をもっと上げたい」と考える方は多いでしょう。
検索結果の上位に表示されることでクリック率が上がり、アクセス数やお問い合わせ数も飛躍的に増加します。
ここでは、初心者でもすぐに実践できる「検索順位を上げるために最低限やっておきたい3つの施策」を紹介します。
1. 定期的にリライトして更新する
検索順位を安定的に上げるには、定期的なリライト(再編集)が欠かせません。
リライトとは、すでに公開している記事の内容を見直し、最新の情報やユーザーニーズに合わせて改善する作業です。
どんなに良質なコンテンツでも、公開当時のままでは検索上位を維持するのは難しいのが現実です。
Googleは「情報の鮮度(更新頻度)」を評価要素の一つとしており、古い情報のまま放置しておくと順位が下がる原因になります。
リライトが必要な主な理由は次のとおりです。
- 古い情報を最新の内容に更新するため
- 競合記事と比較して不足している情報を補うため
- 検索アルゴリズムの変化に対応するため
特に、アクセスが多いページほど定期的に見直すことが大切です。
新しい事例や統計データを追加したり、最新のトレンドを反映させたりして、常に「今の読者に最適な情報」を提供しましょう。
2. ページ表示速度を改善する
検索順位を上げる上で、ページの表示速度(読み込み速度)も非常に重要です。
Googleは「ページエクスペリエンス(UX)」の一環として表示速度を重視しており、遅いサイトは評価が下がりやすくなります。
ユーザーは、ページが3秒以上表示されないと離脱する傾向があります。
表示が遅いとそれだけで閲覧されず、結果的にSEO評価にも悪影響を及ぼすのです。
速度を測定するには、以下のツールが役立ちます。
- Google PageSpeed Insights(ページ速度を数値化・改善提案付き)
- Google Analytics(GA4)(ユーザー行動と速度データを分析)
改善方法としては、まず画像データの圧縮から始めましょう。
不要なプラグインの削除や、キャッシュ設定の最適化も有効です。
もし技術的な部分が難しい場合は、Webエンジニアや制作会社に依頼して最適化を進めると良いでしょう。
3. URLを正規化する
意外と見落とされがちですが、URLの正規化(canonical設定)もSEOの基本施策の一つです。
同じ内容のページが複数存在すると、Googleのクローラーが「どのページを評価すべきか」判断できず、重複コンテンツとして扱われる可能性があります。
例えば、次のようなURLが別ページとして認識されるケースです。
https://example.comhttps://www.example.comhttps://example.com/index.html
これらを放置すると、ページ評価が分散してしまい、検索順位の低下につながります。
URLを一つに統一する「正規化設定」を行い、評価を集中させましょう。
WordPressなどのCMSを利用している場合は、SEOプラグイン(例:All in One SEO、Yoast SEOなど)で簡単に設定できます。
HTML直編集が必要なケースでは、専門家に依頼するのがおすすめです。
できればやっておきたい追加対策
上記3つに加えて、検索順位を安定的に上げたい方は次のポイントも押さえておきましょう。
- 検索対象外ページや低品質コンテンツは noindex 設定にする
→ 内容が薄いページや重複記事をGoogleの評価対象外にすることで、全体の評価を上げやすくなります。 - リンク切れ(404エラー)がないか定期的に確認する
→ リンク切れはユーザー体験を損ね、クローラーの巡回効率も低下します。
これらの小さな改善を積み重ねることで、Googleからの信頼度が高まり、長期的に検索順位の上昇が期待できます。
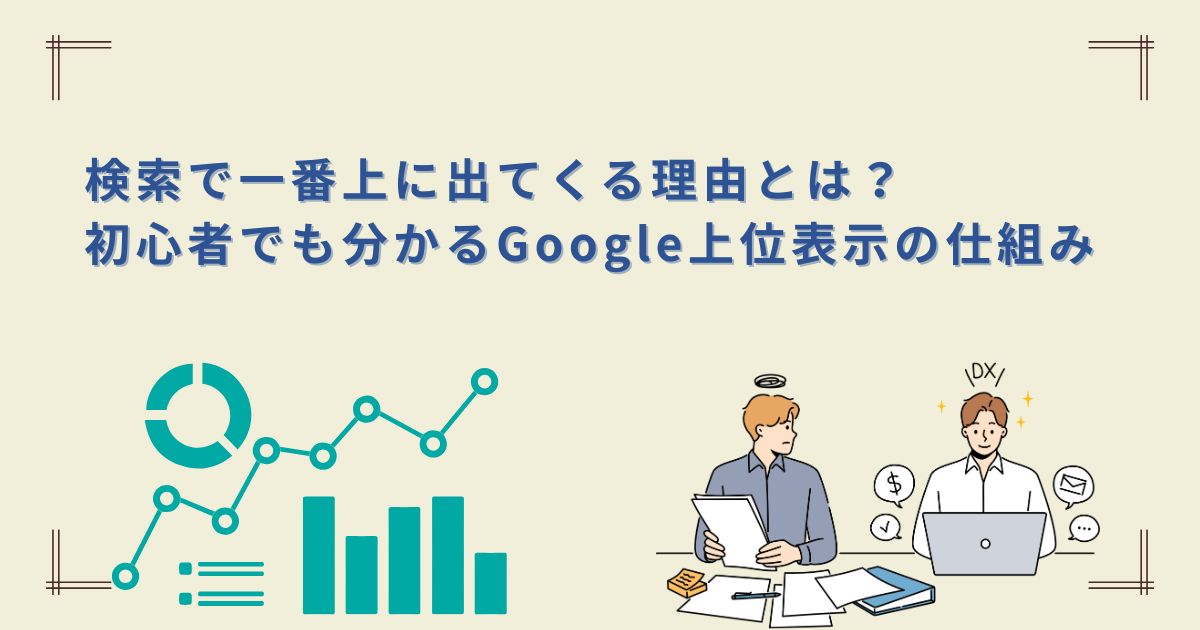
上位表示を狙うのは簡単ではない
ここまで、初心者の方でも実践しやすい基本的なSEO対策をご紹介してきましたが、
「思っていたよりもやることが多い」と感じた方も多いのではないでしょうか。
実際のところ、本業の合間に片手間で上位表示を狙うのは難しいのが現実です。
なぜなら、検索エンジンの評価基準は年々高度化しており、専門的な知識や継続的な改善が求められるからです。
上位表示を目指すのが難しい主な理由は、以下のとおりです。
- 競合対策など、やるべき施策が多すぎる
コンテンツ制作・被リンク獲得・内部構造の最適化など、複数の要素を総合的に行う必要があります。 - SEOや解析に関する専門知識が必要
キーワード戦略やGoogleアルゴリズムの理解、HTML構造の最適化など、専門的な知識を要します。 - 分析や改善のためのツールが不可欠
Google Search Console や Analytics など、データ分析ツールを活用して改善を継続する必要があります。
このように、SEOは「一度設定すれば終わり」というものではなく、
継続的な運用と改善の積み重ねが成果に直結する長期戦です。
そのため、自社メディアを確実に上位表示させたい方は、
SEO専門の業者やコンサルタントに依頼することを検討すると良いでしょう。
専門家に任せることで、最短ルートで効果的な施策を実現でき、
時間とコストの無駄を大幅に減らすことができます。
ホームページが検索されるようにするに関するよくあるご質問
最後に、ホームページが検索されるようにするためのよくあるご質問(FAQ)をまとめました。
基本的なSEO対策から、専門的なテクニックまでを幅広くカバーしています。
ぜひWeb集客の改善にお役立てください。
Q. ホームページをGoogle検索で見つけやすくするには?
A. Googleのインデックス登録が必要です。
XMLサイトマップを作成し、Googleサーチコンソールへ送信することで、検索エンジンにホームページの存在を知らせることができます。
登録が完了していない場合は、URL検査ツールを使ってインデックス登録をリクエストしましょう。
Q. SEOで最も重要なポイントは?
A. キーワード選定とコンテンツの質です。
検索ユーザーが実際に入力しそうなキーワードを設定し、その意図に合った情報を丁寧に発信することが上位表示の基本です。
単なる説明ではなく、「ユーザーの悩みを解決する内容」を意識して作成しましょう。
Q. ホームページのコンテンツを改善する方法は?
A. ユーザーに有益な情報を提供することが最も大切です。
関連キーワードを自然に配置し、最新の情報や事例を定期的に追加しましょう。
古い情報を更新し続けることで、Googleからの評価も上がります。
Q. Googleに早くインデックスしてもらうには?
A. Googleサーチコンソールを利用し、サイトマップ送信とURL検査を行いましょう。
インデックス登録リクエストを送ることで、クロール(検索ロボットの巡回)を促進できます。
Q. SNSを使ったSEO対策は効果的ですか?
A. はい、効果的です。
SNSで自社コンテンツを発信することで、外部サイトからのアクセスや被リンクが増え、間接的にSEO効果が期待できます。
特にTwitter(X)やInstagramなどで更新情報を発信すると、認知拡大にもつながります。
Q. ホームページが検索結果に表示されないときの対処法は?
A. noindexタグが誤って設定されていないか確認しましょう。
また、タイトルやメタディスクリプション、本文に適切なキーワードを含めることも重要です。
検索エンジンに理解されやすい構造へ改善してください。
Q. SEO対策で避けるべきことは?
A. ユーザーに価値のないコンテンツや、キーワードの詰め込みすぎ(キーワードスタッフィング)はNGです。
Googleは、ユーザーの役に立つ誠実なコンテンツを優先的に評価します。
Q. ホームページのローディング速度を改善するには?
A. ページの読み込み速度はSEO評価に大きく影響します。
画像を圧縮し、不要なJavaScriptを削除、キャッシュを活用することで改善が可能です。
「Google PageSpeed Insights」で現状をチェックしてみましょう。
Q. モバイルフレンドリーなサイト設計は重要ですか?
A. 非常に重要です。
Googleはモバイルファーストインデクシングを採用しており、スマートフォンで快適に表示されるサイトを優先的に評価します。
レスポンシブデザインを導入して、あらゆる端末で見やすい構成に整えましょう。
Q. 内部リンク戦略とは何ですか?
A. サイト内の関連ページを内部リンクでつなぐ施策です。
クローラーがページを巡回しやすくなるほか、ユーザーも必要な情報へスムーズに移動できます。
適切なアンカーテキスト(リンク文字)を使って関連性を高めましょう。
Q. 外部リンクはSEOにどのような影響がありますか?
A. 高品質な外部サイトからのリンク(被リンク)は、Googleが「信頼性の高いサイト」と評価する重要な要素です。
ただし、不自然なリンクの購入や相互リンクの乱用は逆効果となります。
Q. リッチスニペットを活用するメリットは?
A. 検索結果に星評価や価格、レビューなどの情報を表示でき、クリック率(CTR)の向上に役立ちます。
スキーママークアップを設定することで、検索結果がより魅力的に見えるでしょう。
Q. ユーザーエクスペリエンス(UX)はSEOに影響しますか?
A. はい。GoogleはUX(ユーザー体験)を非常に重視しています。
わかりやすいナビゲーション、高速な表示速度、明確な構成など、ユーザーがストレスなく閲覧できるサイトを目指しましょう。
Q. HTTPS(SSL)対応は必要ですか?
A. 必須です。
HTTPS化されたサイトは通信が暗号化され、安全性が高くなります。
GoogleはHTTPSをランキング要素の一つとしており、信頼性のあるサイトとして評価します。
ホームページを検索されるようにするならArchRise
ホームページを「検索される状態」にするためには、SEOの知識だけでなく、正確な分析と継続的な改善が欠かせません。
しかし、社内で一から取り組むには時間もリソースも限られており、「何から手をつけていいかわからない」という方も多いのではないでしょうか。
ArchRiseでは、SEO対策・Web広告・サイト改善を一貫してサポートしています。
Googleのアルゴリズムに基づいた正しいSEO戦略はもちろん、検索に強い構成・ライティング・内部リンク設計までトータルで最適化。
「検索で見つかるホームページ」を実現し、集客につながる仕組みづくりをお手伝いします。
まとめ
ホームページを検索結果に表示させるためには、まずGoogleに正しく認識される(インデックス登録)ことが第一歩です。
そのうえで、ユーザーにとって価値あるコンテンツを提供し続けることで、検索エンジンからの評価が高まり、上位表示が実現します。
- インデックス登録やサイトマップ送信で検索される土台を作る
- SEO対策で上位表示を狙う
- 定期的なリライトと改善で検索順位を維持する
これらを地道に積み重ねることで、ホームページは確実に見つけられる存在へと成長します。
もし自社だけでの対応が難しいと感じたら、Web集客の専門家であるArchRiseにご相談ください。
効果的なSEO施策で、御社のホームページを検索される資産へと育てます。