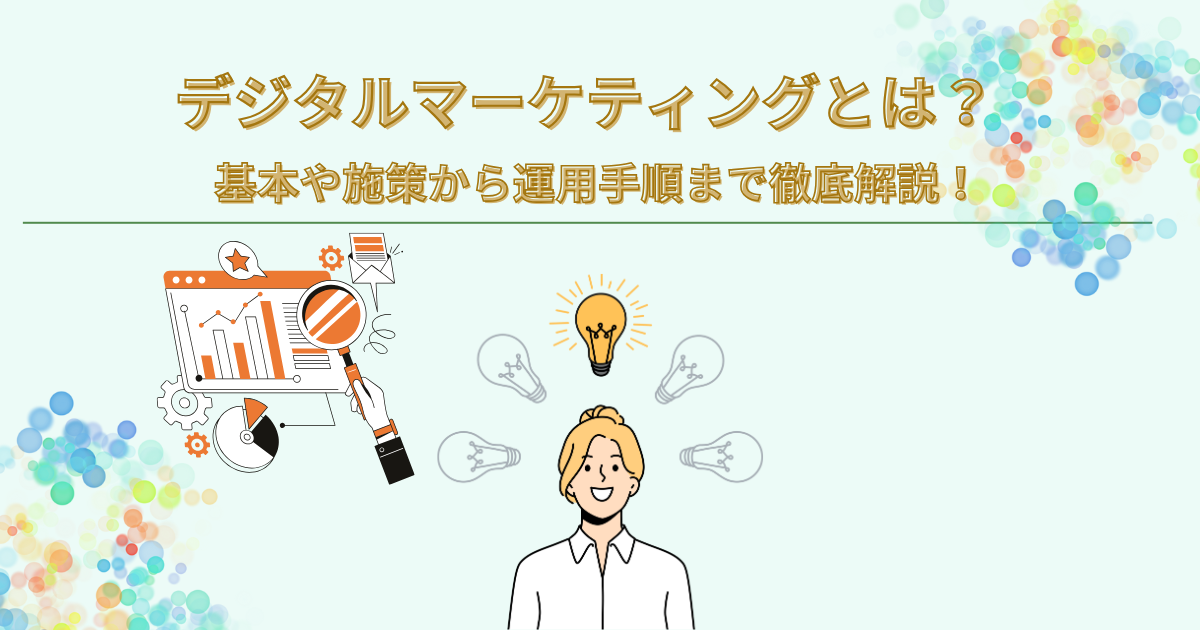インターネットやSNSの普及により、あらゆる業種・業務で顧客との接点がリアルからオンラインへと移行してきました。中でも注目されているのが「デジタルマーケティング」です。製品やサービスの強みを適切なメディアを通じて届けることで、ブランドの価値を高め、顧客とのコミュニケーションを深めることが可能になります。
とはいえ、デジタルマーケティングにおいては、「何から始めればいいのか」「マーケティング戦略としてどのチャネルを選択すべきか」など、迷う点も多いのが実情です。本記事では、デジタルマーケティングの基本的な意味や活用のメリット、具体的な施策やツールの使い方、さらに成功に導く運用のコツまでを徹底解説します。
これから取り組む方も、すでに一部運用している方も、ぜひご覧いただき、ご自身のビジネスに役立つ情報を見つけてください。これからデジタル施策を始めたい初心者の方も、あらためて体系的に整理したいマーケティング担当者の方も、ぜひ最後までご覧ください。
デジタルマーケティングの基本を理解しよう
ここでは、デジタルマーケティングの定義、オフラインマーケティングとの違い、そして今なぜ重要なのかという背景について解説します。
デジタルマーケティングとは?
デジタルマーケティングとは、インターネットやデジタル技術を活用して行うマーケティング活動の総称です。Webサイト、SNS、検索エンジン、メール、アプリなどを通じて、顧客との接点を築き、商品やサービスの訴求・販売促進を行います。従来の広告やチラシなどとは異なり、ユーザーの行動データを取得・分析し、よりパーソナライズされたアプローチが可能です。
オフラインマーケティングとの違い
オフラインマーケティングとは、テレビCM、新聞広告、チラシ、リアルイベントなど、インターネットを介さない形で行われる従来の宣伝手法です。一方で、デジタルマーケティングはWebやアプリ、SNSなどのプラットフォームを活用し、オンラインでの顧客接点を中心に展開します。
大きな違いは、顧客の行動や属性データを蓄積・分析できる点にあります。たとえば、デジタルマーケティングの場合、Webサイトへの訪問者数や広告のクリック率、コンテンツの閲覧時間などを数値で把握できるため、施策の良し悪しをリアルタイムで判断しやすくなります。また、cookieベースのセグメント配信や、行動履歴に基づくリターゲティング施策など、より質の高い顧客体験の提供が可能です。
さらに、デジタルでは一部の施策をA/Bテストしながら素早く改善できる点も大きなメリットとなります。変化する市場や顧客のニーズに対し、柔軟に対応できる体制が整えやすくなります。
なぜ今、デジタルマーケティングが重要なのか
デジタルマーケティングが今、注目されている理由は、人々の購買行動や情報収集の“場所”が大きく変化したからです。スマートフォンやタブレットの普及、SNSや検索エンジンの常時使用により、顧客は実店舗を訪れる前にWebサイトを閲覧し、製品の口コミやブランドの評判を確認するのが当たり前の行動となりました。
このような状況下では、企業が自社の情報や魅力を届けるためには、まずオンラインで見つけてもらう必要があります。つまり、商品やサービスのメリット、強みを的確に伝えるためのマーケティング戦略が、オンライン上で構築されていなければ、そもそも顧客候補のリストにも入らないのです。
また、コロナ禍以降、BtoB市場でもオンラインの商談や情報収集が当たり前となり、リアルイベントや訪問営業に依存しない営業体制の構築が加速しました。こうした変化により、企業の業務全体にデジタル活用を取り入れることが、利益や成長を生み出す鍵となっています。
つまり、デジタルマーケティングは単なる宣伝手段ではなく、顧客情報を蓄積し、カスタマージャーニーに沿って最適なコンテンツを届ける全体最適のシステムとして機能しており、今後さらに必要性が高まると予測されます。
主なデジタルマーケティング施策と特徴
デジタルマーケティングには多様な施策があり、それぞれが異なる目的・ターゲットに対して機能します。この章では、具体的なマーケティング戦略の立案やチャネル選定に役立つ主要施策の特徴を解説します。ブランドの認知度を高めたい場合や、特定の製品を販売促進したい場合など、目的に応じた施策の選び方を知ることが成果への第一歩です。
また、近年では1つのチャネルに依存せず、SEO、SNS、広告などをあらゆるプラットフォームと連携しながら全体を設計する“統合型アプローチ”が主流となっています。施策ごとの強みや相性を理解することで、最適な組み合わせと運用方法を選択できるようになります。ここでは、それぞれの代表的な施策について詳しく見ていきましょう。
SEO(検索エンジン最適化)
SEO(検索エンジン最適化)は、自社のWebサイトやECサイトがGoogleやYahoo!などの検索結果で上位表示されやすくするための施策です。ユーザーが検索するキーワードに対して的確な情報を届けることで、自然流入(オーガニックトラフィック)の増加が期待でき、販売や登録といった利益にもつながります。
主な手法としては、以下のような要素が含まれます。
キーワード調査
ユーザーが何を知りたくて検索しているのかを把握し、適切な言葉を選定します。
内部対策
HTMLの構造や見出しの設計、コンテンツの質などを改善し、検索エンジンに評価されやすい構成に整えます。
外部対策
他社サイトやメディアからのリンク(被リンク)を獲得し、信頼性を高めます。
モバイル対応
スマートフォンやタブレットで閲覧しやすい設計は、ユーザー体験を高め、SEO評価にも影響します。
検索行動はユーザーの関心や問題意識を反映しており、「今、何に注目が集まっているのか」「どんな悩みが存在しているのか」といった市場の動きを知るヒントにもなります。このように、SEOは単なる技術施策にとどまらず、顧客のニーズを読み解くマーケターにとって不可欠な情報資源なのです。また、SEO施策を継続することで、広告とは異なり蓄積型の集客チャネルを構築できる点も大きなメリットです。アクセス数の増加はもちろん、長期的にブランド価値を高める手段としても機能します。
コンテンツマーケティング
コンテンツマーケティングとは、顧客にとって価値のある情報を継続的に発信し、信頼を築いたうえで購買や問い合わせといった行動につなげるマーケティング手法です。単に商品やサービスを宣伝するのではなく、「悩みの解決」「学び」「比較検討」といったプロセスに役立つ情報を提供することで、ブランドとの関係を深めていきます。
具体的には、以下のようなコンテンツが活用されます。
- ブログ記事・コラム:検索流入を意識し、顧客の課題を掘り下げて解決策を提示
- ホワイトペーパー:業務課題に直面する法人向けの資料提供
- 動画・ウェビナー:リアルな製品デモや使用シーンを伝える
- SNS投稿やインフォグラフィック:視覚的に情報を届け、拡散を促進
こうした情報発信は、SEOとの親和性も高く、ユーザーが検索エンジンを通じて自社の製品やサービスを見つけやすくする仕組みを同時に整えることができます。
コンテンツマーケティングの最大の強みは、顧客情報の蓄積とナーチャリング(育成)にあります。たとえば「製品の比較ガイドをダウンロードした人には、後日メールで導入事例を送る」といった流れを設計すれば、顧客の検討段階に応じたアプローチが可能になります。これはカスタマージャーニー全体を可視化した設計といえます。
また、良質なコンテンツは会社やブランドの専門性を強く印象づける手段でもあり、他社との差別化や信頼性の構築にも役立ちます。近年ではBtoB企業でもこの手法を重視するケースが増えており、業界におけるプレゼンス向上にも直結します。
SNSマーケティング(Instagram・X・TikTokなど)
SNSマーケティングとは、Instagram、X(旧Twitter)、TikTok、Facebook、YouTubeなどのプラットフォームを活用し、ユーザーとのコミュニケーションを通じて認知拡大やエンゲージメントの向上を図るマーケティング手法です。リアルな日常に近い感覚で発信できるSNSは、ブランドのイメージ構築や顧客との信頼関係の醸成にとって非常に効果的です。
SNSの最大のメリットは、あらゆる世代・属性の人と接点を持てることと、拡散性が高く、一部の投稿が一気に注目を集める可能性があることです。たとえば、商品レビュー動画がバズることで、実店舗への訪問やECサイトでの販売増加につながるケースも少なくありません。プラットフォームごとの特性を理解して使い分けることが成功の鍵です。
- Instagram:ビジュアルに強く、ライフスタイル系やファッション、飲食、美容などに適しています。ストーリーズやリールを活用することで、製品の使い方や現場の雰囲気をリアルに届けることができます。
- X(旧Twitter):速報性や話題性の高い投稿で拡散を狙える場です。ユーザーとのコメントのやりとりも活発で、マーケターと顧客の距離が近くなるという特長があります。
- TikTok:短尺動画で商品の使用シーンやHowToを感覚的に訴求できます。Z世代を中心とした若年層へのアプローチに強みがあります。
SNSマーケティングでは、広告とオーガニック投稿の両方を組み合わせたハイブリッド運用も有効です。投稿への反応を分析しながら、的確なセグメントに広告を出稿することで、質の高いリードやフォロワーを獲得できます。
さらに、UGC(ユーザー生成コンテンツ)やインフルエンサーとの連携など、「顧客が自ら発信したくなる仕組み」も含めて設計することで、ブランドの広がりはより強固なものになります。
メールマーケティング
メールマーケティングは、見込み顧客や既存顧客に対してメールを通じて情報を届けることで、コミュニケーションを深め、販売促進や関係構築を行う施策です。特にBtoB領域では、カスタマージャーニーに沿った情報提供によって、段階的に関心を高めるナーチャリング手法として活用されます。配信内容は、キャンペーン告知、製品情報、ブログ記事の更新通知、セミナー案内、事例紹介など多岐にわたり、業務上の意思決定をサポートする材料としても役立ちます。顧客情報に基づいたパーソナライズ配信や、MA(マーケティングオートメーション)ツールとの連携により、より細やかなセグメントへの適切なメッセージ配信が可能です。
メール配信は、タイミングや件名、差出人名などの工夫で開封率が大きく変わるため、A/Bテストを行いながら改善していくことが重要です。また、HTMLメールを使えば、視覚的に訴求力の高いコンテンツやCTA(行動喚起)も盛り込みやすくなります。購読者との信頼関係を築くためにも、過度な宣伝ではなく「役立つ情報」や「価値のある提案」を含むことが成功のポイントとなります。
PPC広告(検索・SNSなど)
PPC(Pay Per Click)広告は、ユーザーが広告をクリックするごとに課金される成果報酬型の広告手法で、即効性に優れた施策として多くの企業に利用されています。Google広告やYahoo!広告などの検索連動型広告のほか、Facebook・Instagram・X(旧Twitter)などのSNS広告も含まれます。この施策の大きなメリットは、ターゲットに対して広告を的確に届けられる点にあります。たとえば、検索広告ではユーザーの検索キーワードに連動して広告を表示できるため、購入意欲の高いユーザーを購買直前のタイミングで獲得できます。SNS広告では、年齢・性別・興味・地域などのユーザー属性に応じてセグメント化された配信が可能です。
また、PPC広告は効果測定も容易で、クリック数、コンバージョン数、費用対効果(ROAS)などを可視化できます。継続的なデータ分析により、広告クリエイティブやターゲティング設定を調整し、市場やユーザーの反応に応じた最適化が可能です。
ただし、競合の多いキーワードはクリック単価が高騰する傾向にあるため、CPA(1件あたりの獲得コスト)を意識した運用が求められます。事前に目標とする指標を設定し、柔軟に改善を重ねる運用体制を整えることが重要です。
(参考)
デジタル広告とは?初心者にもわかりやすく解説!
PPC広告とは?よくある疑問や特徴、メリット・デメリットを徹底解説!
ディスプレイ広告と動画広告
ディスプレイ広告とは、Webサイトやアプリ内にバナー画像やテキスト形式で表示される広告を指します。Googleディスプレイネットワーク(GDN)やYahoo!ディスプレイ広告などが代表的なプラットフォームで、特定のメディアやユーザーの興味・行動履歴に基づいたターゲティングが可能です。ブランド認知やリターゲティングに適しており、顧客の訪問履歴や閲覧行動を活かした再アプローチにも役立ちます。
一方、動画広告はYouTubeなどの動画配信サイトを中心に配信される広告形式で、視覚と聴覚を活かしたダイナミックな表現が可能です。特に製品の使用シーンや体験価値をリアルに伝えたい場面において、高い訴求力を発揮します。また、15秒以下のスキップ不可広告や、短尺のバンパー広告など、フォーマットの選択肢も豊富で、目的や商材に合わせた最適な構成が可能です。
ディスプレイ・動画広告ともに、潜在顧客に対する宣伝効果を高めるための重要な手段です。SEOや検索広告ではリーチできない層にまで情報を届けられるため、市場全体でのブランドの存在感を高めたい場合に有効です。また、広告配信後はGoogle広告やYouTubeアナリティクスなどの広告配信ツールを活用し、表示回数・視聴完了率・クリック率・コンバージョン率などを分析することが必須です。こうしたデータ分析によって広告の質を高め、利益につなげる施策を継続的に実施していくことが求められます。
アフィリエイト広告・インフルエンサーマーケティング
アフィリエイト広告とは、他社のブログやメディアに掲載された紹介リンク経由で発生した成果に応じて報酬を支払う仕組みです。クリック単価や成果報酬型など複数のモデルがあり、自社の製品やサービスを広く発信してもらえる仕組みとして、多くのECサイトやサービス事業者が活用しています。特に、認知拡大や販売促進の初期段階でのコストリスクが少ないことがメリットです。
一方、インフルエンサーマーケティングは、SNSで影響力を持つ人物(インフルエンサー)を通じて商品やブランドを紹介してもらう施策です。視覚的に訴えるInstagramやYouTubeなどのメディアプラットフォームを使用することが多く、リアルな体験を通じた発信が可能です。共感や信頼を重視する若年層への訴求に強みがあります。
これらの手法は、顧客情報が蓄積されにくい初期フェーズでもブランドの認知を高めやすく、特定のニッチ市場へのアプローチにも有効です。また、特定ジャンルに強いパートナーを選択することで、より的確なターゲティングが可能になります。
ただし、どちらの手法もコンテンツの質と配信先の選定が成功の鍵です。企業側が押し付けがましくならないよう、インフルエンサーやアフィリエイターとの適切なコミュニケーションとコンテンツ管理が求められます。近年では、カスタマージャーニー上のどのタイミングで訴求すべきかをマップ化し、施策の位置づけを明確にするケースも増えています。
デジタルマーケティングの運用ステップ
ここでは、デジタルマーケティングを実際に運用する際の一連のプロセスについて解説します。計画段階から改善・継続運用まで、体系的に理解することが成功への鍵です。
目的設定とKPI設計
デジタルマーケティングの出発点は、目的の明確化です。売上向上、認知拡大、リード獲得など、自社の事業戦略に即したゴールを設定し、それを数値で管理できるKPI(重要業績評価指標)へと落とし込みます。例えば「月間100件の資料請求獲得」や「広告のCTRを2%以上にする」といった具体的な目標を設けることが、評価と改善の基準になります。
ターゲット設定とペルソナ設計
ターゲットを明確にしないまま施策を展開すると、メッセージが届かず成果も得られません。年齢、性別、職業、ライフスタイルなどのデモグラ情報に加え、価値観や購買動機までを盛り込んだ詳細な「ペルソナ」を設計し、その人物に響く施策を立案することが重要です。ペルソナは社内で共通認識を持つための指標にもなります。
チャネルの選定と戦略立案
設定した目的やターゲットに応じて、どのチャネルを活用するかを決定します。SEOやリスティング広告、SNS、メール、ウェビナーなど、数ある手法の中から、最も効果的な手段を組み合わせて施策を設計する必要があります。また、チャネルごとに異なるKPIや役割を設け、相互補完するように戦略を構築することが成果につながります。
実行・配信と効果測定
準備が整ったら、いよいよ施策を実行します。広告であれば配信、メールであれば送信、ウェブコンテンツであれば公開といったアクションを行い、その成果を数値で測定します。Googleアナリティクスや各広告媒体の管理画面、CRMツールなどを用いて、PV数、クリック数、コンバージョン数などのデータをリアルタイムで確認し、想定通りに動いているかを検証します。
改善(PDCA)と継続運用のポイント
デジタルマーケティングは一度やって終わりではなく、効果測定の結果をもとに改善し、繰り返し最適化していくPDCAサイクルの実践が必要不可欠です。広告文の微調整、クリエイティブの差し替え、ターゲットの見直しなど、改善の余地は常に存在します。継続的に取り組むことで、成果の安定と拡大を実現できます。
BtoBとBtoCで異なる活用方法
ここでは、デジタルマーケティングがBtoB(企業間取引)とBtoC(消費者向け)でどのように異なるアプローチを求められるかを比較・解説します。
BtoBにおけるデジタル施策の組み立て方
BtoBのマーケティングでは、購買プロセスが長期化・複雑化する傾向があるため、リードジェネレーションからナーチャリング(育成)、営業連携までの一貫した設計が求められます。ホワイトペーパー、ウェビナー、メルマガ、MAツールなどを駆使し、段階的に顧客の理解を深めていく手法が効果的です。また、意思決定者に向けた情報設計と、営業との情報共有も重要なポイントです。
BtoC向け施策の特徴と注意点
BtoCの場合、ユーザーの関心や感情に直接訴求するスピード感のある施策が必要です。SNSや動画広告、インフルエンサー施策など、感覚的な訴求と購買動機の刺激が中心となります。デザインやコピーのインパクトが成果を左右する場面も多く、瞬間的な判断で購買される商材では特にクリエイティブの重要性が増します。また、個人情報保護や顧客対応のスピードにも注意が必要です。
デジタルマーケティングに必要なツール
デジタルマーケティングでは、「施策の実行」「効果の可視化」「改善サイクルの実行」において、さまざまなツールが活用されます。ここでは、実務で欠かせない主要ツールをカテゴリごとに紹介し、それぞれの役割と活用ポイントを解説します。
アクセス解析ツール
アクセス解析ツールは、Webサイトの訪問者数、流入元、ユーザー行動などを詳細に分析するための基本ツールです。代表例としてはGoogleアナリティクス(GA4)があり、以下のような分析が可能です。
- ページビューやセッション数の把握
- 流入チャネル(検索、SNS、広告など)の内訳確認
- コンバージョンに至るユーザー行動の追跡
- 地域・デバイス・ユーザー属性別の傾向分析
これらのデータをもとに、Webサイトや広告の改善点を見つけ、施策の精度を高めていくことが可能です。Googleアナリティクスの他にも、Microsoft ClarityやHotjarなど、ユーザーのスクロールやクリックを可視化できるツールも補完的に利用されます。
MA(マーケティングオートメーション)ツール
MA(マーケティングオートメーション)ツールは、見込み顧客への継続的なアプローチを自動化し、効率よくナーチャリング(育成)を行うためのツールです。
代表的なMAツールには以下があります。
- HubSpot
- Zoho Marketing Autoamation
- Pardot(Salesforce)
- BowNow(国産MA)
主な機能には、以下のようなものがあります:
- メール配信やフォーム連携の自動化
- スコアリングによる見込み度の可視化
- 顧客行動の履歴管理(メール開封、資料DLなど)
- 営業への自動アラート送信
MAツールを活用することで、「問い合わせはまだ無いが興味を持っている層」にも継続的に接点を持ち、商談へとつなげる可能性を広げられます。
広告管理・配信ツール
複数の広告チャネルを効率的に管理・配信するには、広告管理ツールが必要です。広告管理ツールの例は以下の通りです。
- Google広告マネージャー:Google検索、YouTube、ディスプレイ広告などの配信管理
- Yahoo!広告マネージャー:Yahoo!検索、ディスプレイ広告などの配信管理
- Meta広告マネージャー:Facebook・Instagram広告のターゲティング・成果分析
- LINE広告マネージャー、TikTok広告マネージャーなど、媒体ごとの公式ツール
広告運用のプロセスは煩雑になりがちですが、これらのツールを使えば、配信設定、ターゲティング、A/Bテスト、成果集計などを一元管理できます。さらにコンバージョンデータと連携すれば、ROASやCPAなど費用対効果をリアルタイムで把握可能です。
(参考)
リスティング広告のやり方を徹底解説!Google広告で成果を出す方法とは?
SEO・コンテンツ分析ツール
自然検索からの流入を増やすには、SEOとコンテンツの最適化が欠かせません。そのための分析ツールとして以下が代表的です。
- Google Search Console:検索キーワード、クリック率、表示回数の分析
- Ahrefs、SEMRush、Ubersuggest:競合比較や被リンクチェック、キーワード調査
- ラッコキーワード、キーワードプランナー:検索ニーズの把握
- SimilarWeb、BuzzSumo:トレンドや競合コンテンツの分析
これらのツールを使うことで、どのキーワードで上位表示されているか、どんな記事が競合で評価されているかを把握し、自社コンテンツの企画・改善に活かすことができます。
よくある課題と失敗例
デジタルマーケティングでは、数値で効果を把握できる反面、分析や戦略が不十分だと成果につながらないことも多くあります。ここでは、実際に起こりがちな失敗パターンとその回避方法を紹介します。
ツールばかりに頼ってしまう
便利なツールが増えてきた一方で、「ツールを導入したから安心」と考えてしまうことは大きな落とし穴です。ツールはあくまで補助的な存在であり、戦略の立案・仮説検証・改善の視点を持たずに使っても、本来の効果は得られません。
例えばMAツールを導入しても、配信するメールの設計やターゲットの精査が甘ければ、エンゲージメントは上がりません。重要なのは、ツール=手段という意識を常に持ち、戦略と実行を両輪で回すことです。
配信して終わりで分析しない
広告やメールを「とにかく出す」ことに注力し、配信後の分析と改善を怠ってしまうケースもよくあります。
「クリック率はどうか?」「コンバージョン率は改善しているか?」「どのチャネルが成果に寄与しているか?」といった視点で配信結果を定期的に検証することで、初めて次のアクションが見えてきます。定期的なレポート作成とKPIモニタリングを習慣化することが重要です。
ターゲットが曖昧で成果につながらない
最もよくある失敗の1つが、誰に向けた施策かが不明確なまま進めてしまうことです。たとえば以下のような状態では、費用対効果が著しく下がります:
- 配信する広告が全世代・全地域を対象にしている
- コンテンツが特定の悩みやニーズに寄り添っていない
- メール配信先が精査されていない既存リスト
対策としては、具体的なペルソナ(仮想の顧客像)を設定し、それに合わせたチャネルやクリエイティブを設計すること。ターゲットに刺さる「課題解決型」のコンテンツを設計することが、成果に直結します。
よくある質問(FAQ)
デジタルマーケティングをこれから始める方にとっては、不安や疑問が多くあるものです。ここでは、よく寄せられる代表的な質問に対して、初心者でも理解できるよう丁寧に解説していきます。
デジタルマーケティングは誰でも始められる?
はい、デジタルマーケティングは基本的に誰でも始められます。特別な資格やライセンスは必要なく、パソコンやスマートフォン、インターネット環境が整っていれば実施可能です。実際、個人経営者やフリーランス、中小企業などが少額の予算からスタートし、成果を出している事例も多く存在します。
ただし、施策の設計・実行・改善には一定の知識とスキルが必要です。ターゲティングの設定、広告配信の最適化、分析ツールの活用など、やるべきことは多岐にわたります。最初は無料のeラーニングや公式ガイド、専門書などで基礎知識を得ながら、少しずつ実践を重ねていくのが現実的です。
また、最近ではツールの操作性も向上しており、ノーコードで利用できるサービスも増えているため、初心者でも取り組みやすい環境が整いつつあります。
どの施策から始めるのがよい?
初めてデジタルマーケティングを行う場合は、「目的とターゲットが明確な施策」から着手するのがベストです。
例えば、以下のような目的別に施策を選ぶのがおすすめです。
- Webサイトへのアクセス数を増やしたい:SEOやGoogle広告(検索連動型)
- すぐに商品を売りたい/問い合わせを取りたい:リスティング広告、SNS広告、LP制作
- 見込み客を育成したい:メールマーケティング、MAツールの導入
- 認知拡大を目指したい:ディスプレイ広告、動画広告、SNS運用
どの施策も一長一短があるため、まずは小さく始めて、反応を見ながら徐々に範囲を広げていくことが重要です。いきなり多チャネルに展開するのではなく、KPIが明確で分析しやすい単体の施策からスタートし、経験を積みましょう。
外注と自社運用の判断基準は?
デジタルマーケティングを外注するか、自社で内製するかは、「社内リソース」「スキルレベル」「費用対効果」の3つを基準に判断しましょう。
自社運用に向いているケース
- 社内にWeb担当者やマーケティング経験者がいる
- すでにGoogleアナリティクスや広告アカウントを活用している
- 費用をできるだけ抑えながら運用したい
- 小規模・中規模の施策をPDCAで素早く回したい
外注に向いているケース
- 初期から高度なノウハウを活用したい
- 社内に人員やノウハウがない
- 運用の時間が確保できない
- LP制作・バナー・動画など制作面のリソースが不足している
特に広告運用やSEOは専門性が高いため、最初は外注で成果の出る仕組みを構築し、後からインハウス化を目指すという段階的アプローチも現実的です。
成果が出るまでの期間は?
施策の種類や目的によって大きく異なりますが、一般的には以下のような目安になります。
- リスティング広告・SNS広告:即日~数週間で反応あり(短期)
- SEO施策・コンテンツマーケティング:3〜6か月以上(中長期)
- MAによるリードナーチャリング:1〜3か月(中期)
- SNS運用によるブランディング:半年以上(長期)
また、広告に関しては初期のテスト期間(1か月程度)を経て、本格運用に入るのが一般的です。すぐに成果を求めすぎると、正確な判断ができないまま停止してしまうケースも多いため、施策に応じた“適切な期待値”を持つことが成功への鍵となります。
株式会社ArchRise はデジタルマーケティングに対応しています。
株式会社ArchRiseは、デジタルマーケティングに関して豊富な実績を有しています。また、リスティング広告やSEO対策やSNS広告、コンテンツマーケティングなど多岐にわたるWebマーケティングサービスを提供しています。豊富な実績とデータに基づいた最適な運用で、クライアント、企業の目標達成を弊社が全力で支援します。
ご相談は無料ですので、興味があればぜひお気軽にお問い合わせください。
まとめ
デジタルマーケティングは、「誰に・何を・どのように届けるか」という本質的なマーケティング思考と、ツールを活用した戦略的な実行力が求められる手法です。
インターネットとスマートフォンの普及により、BtoB・BtoC問わず、オンラインで顧客と接点を持つことがスタンダードとなっています。アクセス解析、広告配信、MA、SEOなど多様な施策が存在する中で、すべてを完璧にこなす必要はありません。
重要なのは、「目的に対して最適なチャネル・手段を選び」「数字を見て継続的に改善する姿勢」です。小さく始めて、失敗と成功を繰り返しながら改善を重ねていけば、確実に成果へと近づいていきます。
初心者でも始められる時代だからこそ、まずは一歩を踏み出し、自社に合った最適なデジタルマーケティングの形を見つけていきましょう。最後までお読みいただきありがとうございました!